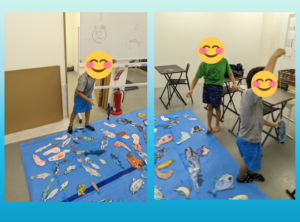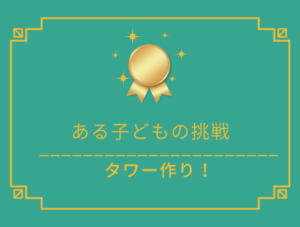岩下修『AさせたいならBといえ』教育新書の書籍を参考にしながら声掛けをしてみています。
声掛けのルールは、本のタイトルの通り、AさせたいならBということ。
例えば、鍋をしっかり洗ってほしいときに、「もっとしっかり洗いなさい」ではなく、
「お鍋をゴシゴシ洗う音が、ここまで聞こえてくるように洗ってごらん」と、そのまま言わない。
Aさせたいときに、Aのままいわない、ということらしいのです。
教室でも発問や、会話のきっかけ、指示を出すときに使ったりしていますが、やはり子供たちの動きがかわります。
セリフづくりにはもう1つルールがあります。それは「ゆれないモノ」をいれること。
「ゆれないモノ」とは、わかりやすく、イメージを頭に長く残すことができるもので、
具体的には、①物 ②人 ③場所 ④数 ⑤音 ➅色。
ゆれないモノのイメージは、頭の中の支えとなり、次の思考をさせることができる、とのこと。
④の「数」のパターンの例。
友達の家に安全にたどり着いてほしいとき。
「気を付けていてらっしゃい」ではなく、
「○○ちゃんの家に行くまでに”いくつ”道路を渡るの?」とすると、頭の中に道路を思い浮かべて数えてくれる。
そこで、「気を付けてね」を言えば、イメージを伴う言葉として頭にとどまる。
②の「人」の例。
交通安全教室にて。
「気を付けよう」「かわいそうだね」の定番の感想に終始するのではなく、
「あなたが交通事故にあったとします。悲しむのは”誰”ですか?」こうすれば、
いやが上にも交通事故を身近に感じざるを得ない。
③の「場所」の例
「バスの運転手さんはどんな仕事をしていますか」ではなく、
「バスの運転手さんは、”どこ”をみて運転していますか。」
すると、信号、バックミラー、料金箱、交差点、バス停、道路、車・・・・などでてきて、
運転手の仕事をより深く理解することができる。
言葉一つで、いろんな想像が膨らみそうですよね・・・。
教室では簡単な例だと、
コンパスで円をかきなさい→10こ円をかいてみて、
ゴミを拾いなさい→ごみを10こ拾おうで、
動きがかわりました。
Aのままいうと、窮屈な感じがするからですかね・・・?
口に出す言葉に、知的な刺激をちりばめられるよう、日々精進したいと思います。